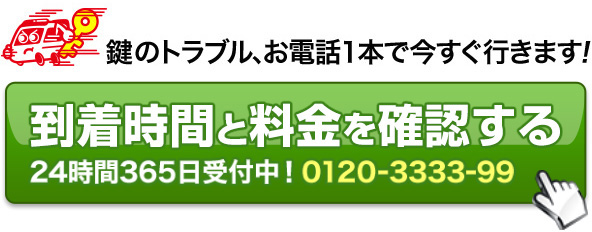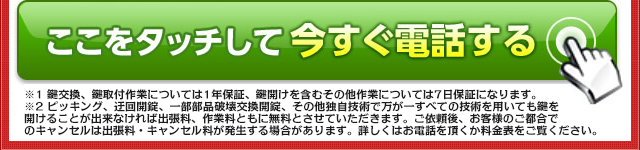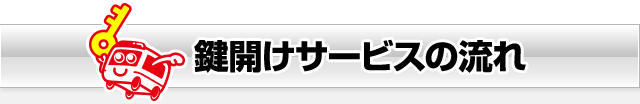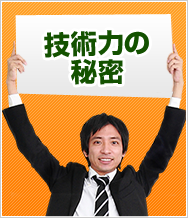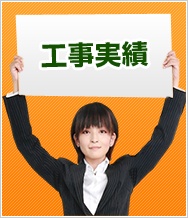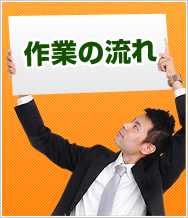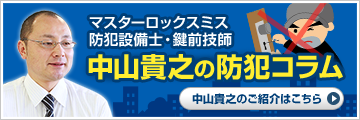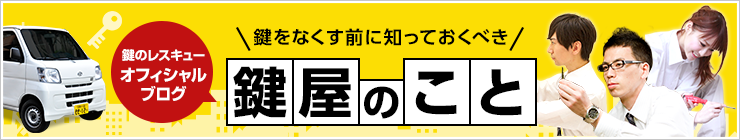- ホーム
- 中山貴之の防犯コラム
- 窓やサッシの鍵(クレセント錠)を交換する方法
窓やサッシの鍵が壊れたら交換しよう

窓やサッシに付いている鍵が壊れたり、調子が悪くなったりしていませんか?
放っておくと窓やサッシがしっかりと閉まらず、窓からの侵入が容易になってしまいます。
そこで、今回は窓やサッシに付いている鍵の交換方法をご紹介します。
また、鍵がゆるい時や固い時の修理方法、メンテナンス方法、防犯性に関することも解説していますので、参考にしていただけると幸いです。
窓やサッシに付いている鍵の名称は?
そもそも窓やサッシに付いている鍵の名称は何というのでしょうか?
それを知っておくと、交換用の鍵を探しやすくなるので、覚えておきましょう。
グレモン錠

ハンドルとロックが一体になっていて、ハンドルを操作するとロックも一緒に動くタイプの鍵です。
ハンドルを動かすだけなので、鍵を挿す必要はありません。
しかし、ハンドルを動かせばよいだけなので、防犯性的には低いです。
グレモン錠は普通の鍵やドアノブに比べてドアを密閉する力が強いため、防音性や防風性に優れています。
そのため、音楽スタジオなどで使われることが多いです。
『グレモン錠』と検索して販売されている商品が、一般家庭の窓に取り付けられていることは多くありません。
大多数の住居では、次に紹介するクレセント錠が使われています。
クレセント錠

クレセント錠はグレモン錠の一種で、ハンドルの部分が三日月(クレセント)のように見えるのが特徴で、一般的な窓やサッシに使われることが多いです。
クレセント錠もハンドルとロックが一体になっているため、防犯性が低くなっています。
今回はクレセント錠を中心に鍵の交換方法などを紹介していきますので、参考にしてください。
クレセント錠の選び方
交換作業を行う前に、新しいクレセント錠を購入しなくてはいけません。そこで悩むのが、どの製品を購入するべきなのかですよね。
基本的には、同じメーカーの同じ型番のクレセント錠を購入するのが楽です。サイズを測ったり、新たに穴を開けたりする必要がないので。
ただ、メーカーや型番が分からない、すでに廃盤になっているなどの場合は、サイズが同じクレセント錠を購入しましょう。
計測が必要な部分は次の3つです。
- ・ビスピッチ
・鍵の高さ
・鍵の奥行
ビスピッチ

ビスピッチとは、ネジとネジの間の長さのことです。クレセント錠を固定している上下のネジの間隔を測ります。
この時、ネジの真ん中から真ん中で測るようにしましょう。
鍵の高さ

鍵の高さは、クレセント錠が取り付けられている位置から、フックになっている部分までの距離のことです。
サッシに接着している部分からフックの奥側の端までの距離を測りましょう。
鍵の奥行

鍵の奥行は、クレセント錠の固定軸とフックの端までの距離のことです。
クレセント錠を固定しているネジの中心から、フックの一番出ているところまでの距離を測りましょう。
窓やサッシの鍵を交換する手順
交換するクレセント錠を選ぶことができたら、交換作業に入っていきます。
交換作業自体はそこまで難しくありません。
なお、この作業は手順などを間違えずに行ってください。些細な失敗でも業者を呼ばなくてはいけなくなってしまいます。
用意する道具

用意する道具は、プラスドライバーです。
1上のネジを外す

クレセント錠を固定しているネジの上のみをプラスドライバーで外します。
外れたら、下のネジを緩めてクレセント錠本体を少しずらしましょう。この時、下側のネジを完全に外さないでください。
2上のネジを仮止めする

先ほど外したネジを上側の穴に入れ直します。この時、クレセント錠を間に挟む必要はありません。
この作業を行わないと、クレセント錠の裏にある板が落下してしまい、クレセント錠の取り付けができなくなります。
裏板が外れてしまった場合は、業者を呼んで窓を取り外しての作業が必要になりますので、絶対に落とさないようにしてください。
3下のネジとクレセント錠を外す

上のネジで裏板を仮止めしたまま、下のネジを外します。これでクレセント錠の取り外しは完了です。
4クレセント錠と下のネジを取り付ける

新しいクレセント錠を下のネジを使って固定します。この時、クレセント錠の上下を間違えないように注意してください。
5上のネジを取り付ける

裏板を止めていた上のネジを取り外し、新しいクレセント錠の上側を固定します。これでクレセント錠の交換作業は完了です。
窓やサッシの鍵がゆるいと思ったら
同じクレセント錠を長く使っていると、鍵にゆるみが出てきます。その時は、ドライバー1本で修理することができますので、試してみてください。
クレセント錠のネジを締め直す

クレセント錠本体がガタガタしている場合は、クレセント錠を固定するネジが緩んでいる可能性があります。
このケースは、クレセント錠を固定しているネジをプラスドライバーで締め直してください。
クレセント錠の受けのネジを締め直す

クレセント錠を受ける部分がゆるくなっている場合は、受けの部分のネジを締め直します。
この時、受けの位置がずれると、うまく鍵がかからなくなるので、上下左右に調整しましょう。
それでも直らない場合は、クレセント錠の交換か、クレセント錠のバネの交換が必要になります。
クレセント錠が固いと思ったら
クレセント錠の動きが固く、鍵の開け閉めに苦労していませんか?
この場合、クレセント錠のメンテナンスを行い、鍵の動きをスムーズにする必要があります。
クレセント錠を外す

まずはクレセント錠を外します。上のネジを外し、下のネジを緩めます。この時に下のネジを緩めすぎないように注意してください。
次に、クレセント錠の上の部分をずらし、上のネジを再度入れ直します。こうすることで、サッシに付いている裏板を仮止めすることができます。
裏板を仮止めした状態で、下のネジを外せば、クレセント錠を外すことができます。
クレセント錠の汚れを落とす

外したクレセント錠をタオルなどできれいに拭いてください。掃除機などでほこりを吸い上げるのも有効です。
受けの部分も汚れていたら、そちらもタオルなどで拭きましょう。
きれいに見えても、隙間などにほこりなどが付着している可能性がありますので、念入りに掃除します。
パーツクリーナーで動きを良くする

クレセント錠にパーツクリーナーなど鍵に使えるスプレーを噴射し、再度タオルなどできれいに拭きましょう。
固さが取れ、潤滑に動くようになったら、クレセント錠をサッシに取り付けて修理完了です。
鍵の位置を調整する

メンテナンスをしても動きが固い場合は、受けとフックに引っかかりが生じている可能性があります。
このケースはクレセント錠の位置、もしくは受けの位置を調整して解決しましょう。
まずは、受けのネジを緩めて、フックがうまく入る位置に動かしてネジを締めます。
受けを動かしてもうまく噛み合わない場合は、クレセント錠側の位置を調整してみましょう。
窓やサッシの位置を調整する

鍵の位置を調整しても固い場合は、窓やサッシの位置がずれていることが考えられます。
このケースは、サッシの高さを調節して建付けを良くすることが解決策です。
サッシの下に調節ネジが付いているので、サッシを上げたり下げたりして建付けを良くしていきます。
この時、調節ネジをすべて外さないことと、サッシや窓が倒れないように注意して作業を行ってください。
メーカーによって調節方法がことなりますので、説明書を確認しましょう。
クレセント錠のバネ交換で直ることも
- ・クレセント錠を動かしても手ごたえがない
・勝手にハンドルが下がってしまう
などの症状がある場合、クレセント錠の内部にあるバネが故障していることが考えられます。
このケースは、クレセント錠そのものを交換しなくても、内部のバネを交換することで解決可能です。
交換するバネは、クレセント錠のメーカーや型番、サイズなどを調べた上で購入してください。
1クレセント錠を外す

まずはクレセント錠を取り外します。上のネジをプラスドライバーで外し、下のネジもクレセント錠が動く程度に緩めます。
この時、下のネジを緩めすぎないように気を付けてください。
その後、クレセント錠を挟まずに上のネジを取り付けます。これにより、裏板を落とさないようにすることができます。
上のネジで裏板を止めた状態で、下のネジを外し、クレセント錠を取りましょう。
2バネを交換する

取り外したクレセント錠の内部にバネが入っているので、マイナスドライバーなどを使って取り外します。
その後、新しいバネをクレセント錠に取り付けてください。バネがうまく伸びなくて取り付けにくい場合は、バネに紐などを通して、引っ張ると取り付けやすいです。
3クレセント錠を取り付ける

バネを交換したら、クレセント錠を元通りに付け直せば作業完了です。
窓やサッシの鍵交換だけではない防犯性の高め方
窓やサッシの鍵を交換して鍵がうまく閉まるようになっても、防犯性が高まったとは言えません。
油断していると空き巣に入られてしまうかもしれません。
ここからは、窓の防犯性を高める方法をご紹介します。空き巣から家を守るためにも、できることがあればやってみてください。
補助鍵の設置

簡単に防犯性を高められるのは、補助鍵の設置です。
クレセント錠が開けられたとしても、補助鍵がロック機能を果たしてくれます。
取り付けも、穴を開けてしっかり固定するタイプから、サッシに挟むだけのもの、両面テープで固定できるものまで様々ありますので、用途よって選びましょう。
また、高いところに取り付ければ、子供が窓を開けられなくなるので、転落防止にも役立ちます。
防犯フィルムを貼る

クレセント錠を開ける方法として多いのが、ガラスを無理やり破ることです。
なので、窓ガラスを破られなければ、空き巣の侵入を防ぐことができます。
窓ガラスを割られないためには、防犯フィルムの貼り付けがおすすめです。防犯フィルムを貼ると、バットやハンマーなどの衝撃でもガラスが割れなくなります。
物によっては、焼いて壊す方法やアイスピックなどでついて壊す方法に弱いものもありますので、注意してください。
窓に柵を取り付ける

ガラスを破られたとしても、室内に入ることができなければ、何も盗まれずに済むかもしれません。
そこで有効になるのが、柵や格子です。体が通らないので、室内への侵入を防ぐことができます。
注意点として、外側から外されないようにすることが大切です。外されては元も子もありません。
外側から外れないようになっている防犯性能の良い製品もあるので調べてみましょう。
外側に鍵を後付けする

鍵穴付きの鍵を窓の外側に取り付けて、クレセント錠が開けられても窓が開かないようにする対策です。外側から鍵が見えるので、空き巣犯に対する抑止力になります。
外側へ鍵を後付けするには、サッシに穴を開ける必要があり、失敗するとガラスが割れてしまう恐れがあります。
後付けする際は、鍵屋さんや工務店さんに依頼するのが安全でしょう。
まとめ
窓やサッシの鍵交換方法をご紹介してきました。古くなったり、壊れたりしたらなるべく早く交換して、鍵が正常に動くようにしましょう。
また、窓の防犯対策はしっかりと行って、空き巣から財産をしっかりと守ることが大切です。

![[安心と信頼の鍵屋さん][日本全国対応]](/assets/img/common/service.png)
![鍵開けなら24時間365日、日本全国対応します!0120-3333-99[スマホ・携帯PHS対応!]](/assets/img/common/tel.png)