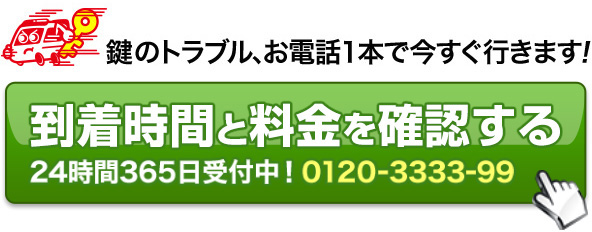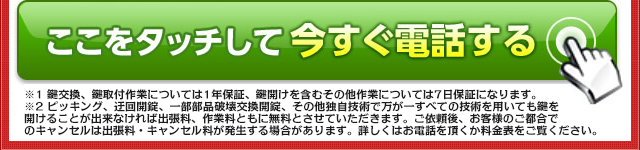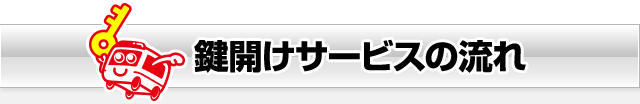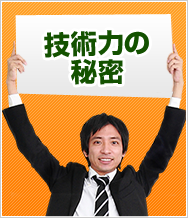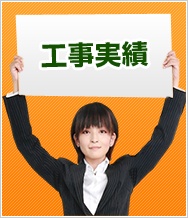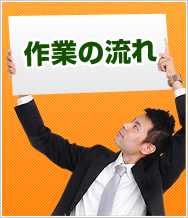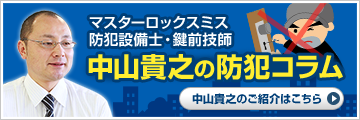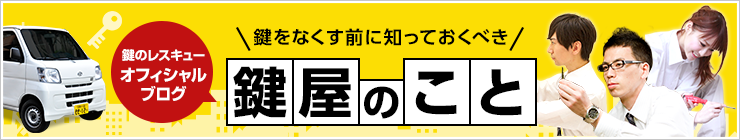- ホーム
- 鍵屋さんの防犯コラム
- 高齢者施設で2人殺害、元職員が“暗証番号解除”で侵入か
高齢者施設で2人殺害、元職員が“暗証番号解除”で侵入か
高齢者施設で2人殺害された事件について、暗証番号で電子錠を解除して侵入した可能性があり、暗証番号運用の落とし穴を鍵の専門家視点で解説します。
高齢者施設で2人殺害 元職員、暗証番号を使い侵入か
事件の経緯と逮捕状況
2025年10月15日未明、埼玉県鶴ケ島市の高齢者施設「若葉ナーシングホーム」で、入居していた女性2人が殺害される事件が発生。うち、小林登志子さん(89歳)への殺人容疑で、元施設職員の 木村斗哉容疑者(22歳) が逮捕されました。木村容疑者は、2人の殺害を認めており、事前に凶器とみられるナイフを購入していたと説明されています。また、捜査当局の取材によれば、16日、木村容疑者が「2人に恨みはなかった」と供述していることが判明しました。
侵入手段と施設のセキュリティ状況
施設の防犯カメラには、刃物を手に歩く人物の映像があり、近隣で自転車に乗る姿も確認されていました。身柄確保時には、血の付いたナイフや衣服、マスクが入ったバッグ、自転車も押収され、注目すべきは、木村容疑者が施設への侵入にあたって、職員用出入口の 4桁暗証番号式電子錠 を使ったとみられる点であります。こじ開けた跡はなく、元職員であった木村容疑者は在職時に把握していた番号をそのまま使用した可能性があります。
リスクと防犯観点からの考察
元職員や退職者のアクセスリスク
今回の事件で最も目立つのは、かつて施設で働いていた元職員が、在職時に知っていた番号で侵入できてしまった可能性が示唆される点です。木村容疑者は、以前この施設で介護士として勤務しており、入居者とほぼ同じ時期に在籍していたという報道もあります。だが、在職中に把握していた暗証番号を、退職後も使える状態にしておくという運用ミスは、外部者では到底及ばない“内部者のリスク”を招くことになり、従業員・職員が退職・異動した際は、即座にその人のアクセス権を抹消する対策が必要があります。
共通番号運用・番号未更新の脆弱性
本件では施設が複数の入口や施錠箇所において同一番号を使用していたという指摘があります。そのような共通番号運用は、番号漏洩・推測のリスクを高めるだけでなく、一箇所突破で敷地全体へのアクセス可能性を広げてしまいます。もし出入口ごとに異なる番号に設定・変更していれば、被害の拡大を部分的に抑えられていた可能性があるのです。
電子錠・スマートロック製品選定と管理のポイント
電子錠を選ぶ際は、暗証番号だけに頼るタイプよりも、カード認証・指紋認証・スマートフォン連携など複数の認証方式を組み合わせたものを選ぶとよいです。ログ閲覧機能やユーザー管理(登録・抹消)機能がしっかりしているか、改ざん防止策が備わっているかという点も、信頼できる製品選定の条件と言えます。暗証番号式鍵・電子錠には、金属鍵と比較して鍵紛失のリスクが低く、取りまわしが良いという利便性の魅力もあります。だからこそ運用設計が甘くてはその強みが裏目に出ます。今回のような事件を防ぐには、製品選定とその後の運用設計を両輪で強化する必要があります。
まとめと専門家の視点
今回の事件は、暗証番号式鍵という「便利さ」を持つシステムが、運用ミスによって侵入手段になりうるという典型例とも言えます。セキュリティ機器そのものの強度に加えて、「運用設計」「アクセス権管理」「ログ監視」「定期更新」というプロセス設計が、鍵管理・施設防犯において決定的な役割を果たします。読者・施設管理者の方には、単に鍵・錠前製品を選ぶだけでなく、運用・管理体制を含めたトータルな防犯設計を見直すことを強く推奨します。
電子錠の取り付けは鍵のレスキューにお任せ
電子錠の取り付けは、実績と技術力のある鍵のレスキューにお任せください。ドアの種類やご希望の機能に合わせて最適な製品を提案し、丁寧かつスピーディーに施工します。ご相談は24時間いつでもフリーダイヤルまでどうぞ!

![[安心と信頼の鍵屋さん][日本全国対応]](/assets/img/common/service.png)
![鍵開けなら24時間365日、日本全国対応します!0120-3333-99[スマホ・携帯PHS対応!]](/assets/img/common/tel.png)